1. 省エネ基準適合とは?
近年、省エネ性能の向上は建築業界における重要なテーマの一つとなっています。特に2025年4月以降、すべての新築建物に対し、省エネ基準適合の義務化が適用されることとなり、これまで300㎡以下の建物には適用されていなかった基準が、一気に拡大されます。
これにより、設計・施工の段階からエネルギー消費量の削減を考慮する必要があり、適合判定(省エネ適判)を受ける手続きも強化されます。本記事では、省エネ基準適合の最新動向と手続きについて詳しく解説します。
2. 省エネ基準適合義務化の背景
国はカーボンニュートラル(2050年の脱炭素社会実現)を目標に掲げており、その達成に向けた建築業界の省エネ対策強化が求められています。2021年4月の法改正では、300㎡以上の非住宅建築物に対して省エネ適判が義務化されましたが、2025年4月の改正により、すべての新築建物が省エネ基準に適合する必要があります。
これにより、設計事務所や工務店などの関係者は、省エネ基準適合を前提とした設計を行う必要があり、適合しない建物は確認申請が通らないため、注意が必要です。
3. 省エネ適判とは?
省エネ適合判定(省エネ適判) とは、建築物の省エネ基準適合性を審査するプロセスのことを指します。具体的には以下の2つの基準を満たす必要があります。
• 外皮性能基準(断熱性能)
• 一次エネルギー消費量基準(設備の省エネ性能)
住宅・非住宅を問わず、省エネ適合判定を受けることで、基準適合の証明書(適合判定通知書)が発行され、建築確認手続きと連動する形で進められます。
4. 省エネ基準適合の手続きの流れ
省エネ適合手続きには以下のプロセスが含まれます。
① 省エネ基準の適合確認
設計の段階で、対象建築物が以下のいずれかの方法で省エネ基準を満たす必要があります。
• 使用基準:断熱材の厚みや窓の性能など、定められた仕様を満たしているかチェック
• 計算ルート:エネルギー消費量をシミュレーションし、基準値内であるか確認
② 省エネ適合判定の申請
所管行政庁や省エネ適判機関に申請を行います。
③ 省エネ適合判定通知書の発行
適合判定が完了すると、「適合判定通知書」が発行され、建築確認申請時に添付することで手続きが完了します。
④ 完了検査
工事完了時に、省エネ基準に適合しているか最終チェックが行われ、問題なければ検査済証が発行されます。
5. 省エネ基準適合が必要な建築物とは?
2025年4月以降、以下のような建築物が省エネ基準適合の対象になります。
適合義務のある建築物
• すべての新築建築物(住宅・非住宅問わず)
• 増改築(10㎡超の増築部分)
適合義務が免除される建築物
• 文化財、応急仮設建築物、仮設工業建築物
• 延べ面積200㎡以下の平屋建物(ただし、省エネ計算は必須)
これまで適合義務がなかった小規模建築物も対象となるため、設計者や施工者は、今後の手続きを確実に把握しておく必要があります。
6. 省エネ基準適合の具体的な対策
① 断熱性能の向上
• 高性能断熱材 の使用
• 高断熱窓(Low-E複層ガラス等)の採用
• 気密性能の向上
② 設備の省エネ化
• 高効率エアコンや換気設備 の導入
• LED照明 の使用
• 再生可能エネルギーの活用(太陽光発電など)
③ 省エネ計算の活用
• 建築設計の段階で省エネ計算を行い、基準適合を確認
• 外皮性能と一次エネルギー消費量をバランスよく最適化
7. 省エネ基準適合の課題と今後の展望
① 手続きの煩雑化
省エネ適判の義務化により、設計者や施工者の負担が増加します。特に、計算が必要な場合、設計の自由度が制限される可能性があるため、事前に対策を講じることが求められます。
② 省エネ技術の向上
市場では、省エネ基準を満たすための建材や設備が急速に進化しており、導入コストも下がりつつあります。最新の技術動向を把握し、適切な設備選定を行うことが重要です。
③ 省エネ住宅の普及
省エネ基準適合は、単なる法規制の対応ではなく、建物の価値向上やエネルギーコスト削減につながります。今後、省エネ性能を強化した住宅やオフィスビルが市場で高評価を受ける流れが加速するでしょう。
8. まとめ|2025年の法改正に向けて準備を進めよう!
2025年4月からの省エネ基準適合義務化により、すべての新築建築物は省エネ適合判定を受ける必要があります。設計や施工の初期段階から適合基準を意識し、適切な断熱材・設備の選定、事前の省エネ計算を行うことでスムーズな手続きが可能になります。
特に設計事務所や工務店は、省エネ適合を前提とした設計フローを構築し、適合判定の手続きに備えることが求められます。最新の省エネ技術を活用しながら、法改正に適応できる準備を進めていきましょう!



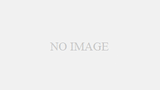
コメント